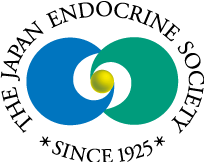学会の発展の鍵は、『多様性(ダイバーシティー)』にあると言われます。性別、年齢、国籍だけでなく、専門(臨床、基礎研究、内科、外科、小児科…)、所属(大学、病院、企業、研究所・・・)、職種(医師、博士、医療専門職・・・)、研究対象(ヒト、動物、細胞、分子レベル・・・)など、多様性とは学問の質にも関わる重要な鍵です。
男女共同参画推進委員会(JES We Can: Japan Endocrine Society Women Endocrinologists Association)は、学会の多様性を目指す活動の一翼を担っています。その活動やロールモデルを紹介すべく、リレーメッセージを企画しました。ひとつひとつのメッセージから感じ取っていただくことがあると思います。是非、お読みください。
大切にしてきたこと
勤医協中央病院 糖尿病内分泌内科
湯野 暁子
このリレーメッセージを担当されている諸先生方のお話や、JES100周年記念エッセイを拝読し、世界の内分泌学をリードされてきた偉大な先輩方の、医学研究者・臨床医としての熱意と努力に、あらためて深い尊敬の念を抱いています。
私は大学卒業後から現在に至るまで、一般病院で勤務してきました。2010年から1年間、国立病院機構京都医療センター臨床研究センターへ国内留学の機会を得ることができました。当時センター長であった島津 章先生(現・淡海医療センター顧問)へ研修を希望するお手紙を直接お送りし、お返事をいただくまで大変緊張して待っていたことを、今でもよく覚えています。
 「たった1年ですが、内分泌の臨床も研究もやりたい」という、今思えば無謀ともいえる私のお願いに対し、臼井 健先生(現・静岡社会健康医学大学院大学 研究科長・教授/静岡県立総合病院ゲノム医療センター長)が、辛抱強くご指導くださいました。北海道に戻ってからもご指導いただき、論文をまとめ、国際学会に参加する機会にも恵まれました。内分泌学を究めようとする若手医師たちと切磋琢磨できた経験は、今も大きな財産です。現在に至るまで、日常診療や学術面で助言をいただくことができ、私の内分泌科医としての基礎を築くことができた1年間でした。
「たった1年ですが、内分泌の臨床も研究もやりたい」という、今思えば無謀ともいえる私のお願いに対し、臼井 健先生(現・静岡社会健康医学大学院大学 研究科長・教授/静岡県立総合病院ゲノム医療センター長)が、辛抱強くご指導くださいました。北海道に戻ってからもご指導いただき、論文をまとめ、国際学会に参加する機会にも恵まれました。内分泌学を究めようとする若手医師たちと切磋琢磨できた経験は、今も大きな財産です。現在に至るまで、日常診療や学術面で助言をいただくことができ、私の内分泌科医としての基礎を築くことができた1年間でした。
写真① Journal Club 京都医療センター / とにかく、たくさんの論文を読みました
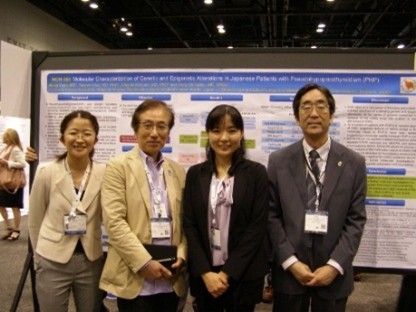

写真②(左)国際内分泌学会/米国内分泌学会会議(ICE/ENDO 2014)シカゴ / ご指導いただいた先生方と
写真③(右)内分泌代謝UPDATE2011 札幌 / 切磋琢磨する仲間に出会えたことが財産です
当時、医療従事者である夫は休職し、7歳、5歳、3歳だった3人の子どもを連れて、家族で京都での1年間を過ごしました。私が卒業した頃は臨床研修制度が必修化される前で、出産・育児をしながら専門医取得の準備を始めることができました。夫の全面的なサポートと、周囲の理解と協力があったからこそ、自分のペースでキャリア形成ができたことに、深く感謝しています。
医師になってから初めて全国学会に参加したのは、第82回日本内分泌学会学術総会(群馬大学、森 昌朋会長)で、医師8年目のことでした。仕事と子育てに追われ、静かな時間を確保できない時期が長く続いていた中で、見るもの、聞くものすべてが新鮮で、学ぶことの楽しさに心が躍ると同時に、自身の知識の不十分さを痛感した学会でもありました。もともと勉強することは好きで、子どもたちが小学校に上がってからは、机を並べて一緒に勉強する時間が増えていきました。
臨床医として私が大切にしていることは、「患者から学び、患者とともに、より良い医療を追求すること」です。得られた知識や技術、経験を、地域に必要とされる医療に生かすため、常に柔軟に自分の役割を考えるよう心がけてきました。現在は病院管理者としての役割も担い、病院経営をめぐる厳しさの中で、より良い医療を追求することの難しさを日々感じていますが、「誰のために、何のために」という軸を忘れず、学びと実践を続けていきたいと考えています。
先日、20歳になった大学生の長女から、「お母さんは、どんなふうに子育てをして、私たちをこんなふうに育てたの?」と突然尋ねられました。なんとも答えの難しい質問です。私は実母を早くに亡くしており、身近な母親像がありませんでした。医師になってから北海道へ来たため、頼れる人も少なく、慣れない土地での子育ては、育児書どおりにいかないことばかりでした。
どんなふうに、という明確な答えがあるわけでもなく、とにかく必死でした。研修時期と出産・育児の時期が重なり、5~6年間はまとまった睡眠をとれない日々が続き、ほとんど眠れないまま仕事に向かうこともしばしばありました。子どもが病気をすれば、夫と交代で仕事を調整し、まさに綱渡りの毎日で、心が折れそうになることも少なくありませんでした。反抗期には、ハラハラしたり、イライラしたりと、自分の感情のコントロールと忍耐力を、これでもかというほど試されました。帰宅が遅いため、朝のうちに弁当作りと夕食のおかずを用意してから出勤する生活を、我ながら長い間よく続けていると思います。
今、子どもたちが成長して振り返ると、思い出されるのは日常の何気ない可愛らしい姿や言葉ばかりで、幸せな時間と、思いがけないほど大きなご褒美をもらってきたのだと感じます。長男が生まれたばかりの頃、「この子の目には何が映っていて、何を考えているのだろう」「大切に育てたいけど、大切にするとはどういうことなのだろう」と頭でっかちに考えてばかりいました。真面目で成績優秀、負けず嫌いな医師が子育てをすると、「正解」を求めてしまうのかもしれません。思いどおりにならないことばかりの子育てを通して、「正解」はその子自身の中にしかないのだと考えるようになりました。彼らがどのような生き方を選択しても、常に愛情をもった応援団長でありたいと思っています。
子育て談義のようなリレーメッセージになってしまいましたが、医師として、そして母親として、心が折れながらもとにかく続けてきたことを、今は誇りに思っています。かけがえのない家族がいるからこそ、医師である私がいます。穏やかな日常に、心から感謝しています。
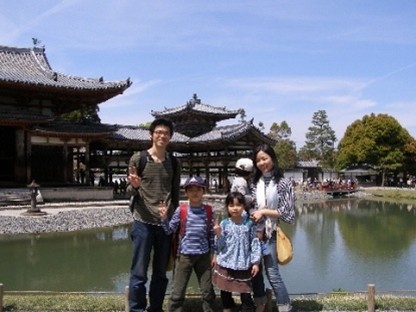
写真④ 世界遺産平等院 宇治(2011) / 5人がそろって前を向いた写真って、とても少ない…
これまでのリレーメッセージ
静岡での仕事とくらし(2025年10月)
静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌代謝センター 小杉 理英子
いくつになっても夢を持つ ~内分泌代謝内科医として歩んだ26年~(2025年6月)
公立陶生病院 内分泌・代謝内科 赤羽 貴美子
内分泌代謝内科医としての今までとこれから(2024年9月)
独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 吉田 守美子
自分自身であり続ける(2024年2月)
島根大学医学部内科学講座内科学第一(内分泌代謝内科) 守田 美和
産婦人科医として考えること(2023年5月)
島根大学 医学部 産科婦人科 折出 亜希
様々な多様性が活きる内分泌診療へ、そして医療者教育へ(2023年3月)
岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)総合内科学 くらしき総合診療医学教育講座
岡山大学病院 内分泌センター 三好 智子
小児内分泌科医の立場から
ー日本小児内分泌学会(JSPE)における10年間の女性医師の動向調査についての報告ー
(2022年8月)
医療法人 むらしたこどもクリニック 理事長
日本小児内分泌学会 男女共同参画・ワークライフバランス委員 村下 眞理
areからwereへ(2022年7月)
政策研究大学院大学 名誉教授、跡見学園女子大学 心理学部臨床心理学科 特任教授
鈴木(堀田)眞理