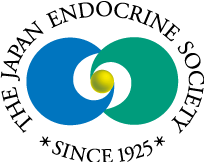2025 Symposium for Academia, Research, and Industry & Autumn Congress of the Korean Endocrine Society (KES)への参加報告
2025年12月16日
◆JES-KES joint symposium “Organ cross-talk in metabolic diseases”
東北大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝・内分泌内科学分野 今井 淳太
名古屋大学環境医学研究所 分子代謝医学分野 伊藤パディジャ 綾香
2025年10月30日~11月1日にかけて、韓国・釜山(Lotte Hotel Busan)にて開催された韓国内分泌学会秋季会議(Autumn Congress of the Korean Endocrine Society)に、日本内分泌学会の推薦を受けて参加致しました。

JES-KES joint symposium “Organ cross-talk in metabolic diseases”では、日韓双方の研究者より、最新の研究成果が発表されました。名古屋大学・伊藤は「慢性炎症と代謝性疾患における免疫代謝リプログラミングと神経‐免疫クロストーク」について、東北大学・今井は「ニューロンを介した肝臓-膵β細胞の臓器間クロストークによるβ細胞の制御」について研究発表を行いました。また、韓国内分泌学会からも2名の研究者から「授乳中の膵β細胞と脂肪組織における代謝リプログラミング」、および「p21-activated kinase 4によるエネルギー代謝恒常性維持」について発表されました。いずれの研究発表に対しても活発な質疑が行われ、臓器間ネットワーク、代謝恒常性、免疫代謝の観点から、有意義なディスカッションが交わされました。
JES We Can session “Empowering diversity in Asian endocrinology”(後述)では、JES We Canの活動内容が紹介され、研究教育、キャリア支援の観点から日韓両学会におけるDEI(Diversity, Equity & Inclusion)に関する取り組みについて意見交換が行われました。特に、KESのDEI委員会は、立候補により選出された11名の若手研究者で構成され、性差に留まらない多様性について幅広く活動を推進している点が印象的でした。
会期中の夜に開催された懇親会では、韓国内分泌学会の理事の先生方はじめ、多くの先生方と研究交流のみならず、両国の内分泌学会に関して意見交換を行うことができました。JESとKESの交流は、両国の先生方が長年にわたり築かれた強固な信頼関係と人脈のうえに成り立っていることを改めて実感し、学会連携の重要性と、その一端を担わせて頂いたことへの感謝の気持ちを強く感じました。
今回の国際学会参加を通じて、日々の研究や診療に還元できる多くの知見と刺激を得ることができました。今後、この貴重な経験を日本内分泌学会の活動にも還元し、日韓をはじめとした国際的な研究交流のさらなる発展に貢献していきたいと考えております。このような貴重な機会を賜りました日本内分泌学会に深く感謝申し上げます。
◆JES We Can session “Empowering diversity in Asian endocrinology”
浜松医科大学 国際化推進センター 山下 美保
東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 槙田 紀子
このたび2025年10月30日~11月1日に開催されたKorean Endocrine Society(KES)の2025 Symposium for Academia, Research, and Industry & Autumn Congressで、JES We Can合同セッションが開催され、参加する機会をいただきました。このセッションが開催されるきっかけとなったのは、第98回日本内分泌学術総会JES We Can企画「ダイバーシティー・国際化」で、KESで初めて女性として学会長(President)に就任されたProf. Eun Gyoung Hongにご講演いただき、その際、今後JES We Canとしても是非交流を深めていきたいとお話したことでした。このシンポジウムはSeoul International Congress of Endocrinology and Metabolism(SICEM)と同様、KES主体の学術集会であり、今回はプサン(韓国)で行われました。
セッションは「Empowering diversity in Asian endocrinology」と題して行われました。最初の講演は「JES we can: From dawn to leadership and beyond」と題して槙田紀子(JES We Can副委員長)から、これまで15年間のJES We Canの歩みを振り返るとともに、100周年に向けて実施中のアンケート結果の一部(DEI関連)を共有し、JESにおける現状と今後の課題について報告しました。
二つ目の講演は「Values in action: The journey of the Korean Endocrine Society’s DEI Committee」と題してKESのDEI committee member最年少であるIn Sun Goak先生から2025年に新規に立ち上がったDEI委員会の設立について、その背景、掲げられたビジョン、初期活動、そして今後の方向性の概要が話されました。山下美保(JES We Can国際化委員会委員長)からは「Diversity from the roots」と題して、男女共同参画白書をもとに日本における女性医師の抱える課題を提示し、それに対する具体的な対策として地方(静岡県)が行っている取り組みについて講演しました。
その後、講演を行った3人とKES診療ガイドライン委員会Mi-Kyung Kim代表でパネラーディスカッションが行われ、フロアからは今後のDEIへの課題や対策について質問があがり、意見が交換されました。興味深かったのは、KESのDEI委員が公募で行われたため性別・年齢も幅広い中、自由に議論が行われて進められているということでした。JES We Canについても質問があり、特にアンケート調査については大変興味を持たれた印象でした。二国が抱える課題は似ているところが多く、良い取り組みはお互いに参考にできるという共通認識をもつことができました。

夜には座長の労とお取りいただいた下村伊一郎先生、JES/KES合同シンポジウムでご講演された今井淳太先生と伊藤パディジャ綾香先生とご一緒にKESとの懇親会に参加させていただきました。リラックスした中でKESの方々と親睦を深めることができ、今後の更なる交流を深めていけると感じました。
ESROC2025への参加報告
2025年6月10日
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
坂東 弘教
 この度、代表理事の有馬寛先生、国際交流委員会委員長の柴田洋孝先生、そして国際交流委員会の諸先生方のご推薦を賜り、第17回アジア糖尿病学会(AASD 2025)および第46回台湾糖尿病学会並びに内分泌学会年次総会(Diabetes Association and the Endocrine Society of the R.O.C. (Taiwan))に参加させていただきました。本学会は、2025年3月28日から30日まで、台北国際会議センター(Taipei International Convention Center)にて開催されました。
この度、代表理事の有馬寛先生、国際交流委員会委員長の柴田洋孝先生、そして国際交流委員会の諸先生方のご推薦を賜り、第17回アジア糖尿病学会(AASD 2025)および第46回台湾糖尿病学会並びに内分泌学会年次総会(Diabetes Association and the Endocrine Society of the R.O.C. (Taiwan))に参加させていただきました。本学会は、2025年3月28日から30日まで、台北国際会議センター(Taipei International Convention Center)にて開催されました。
AASDが主軸となる学会であったため、糖尿病に関するセッションが多く開催されていた中で、私が担当した下垂体セッションをはじめ、副腎、甲状腺、骨粗鬆症など、内分泌分野に関連するセッションも数多く企画されていました。著名な海外の研究者が多数招待されており、台湾内分泌学会が積極的に海外交流を進め、さらなるレベル向上を目指していることを現地で強く実感しました。台湾からの発表では、National databaseを活用した研究がいくつか行われ、さまざまなジャーナルに報告されています。本邦においても、このような研究を発展させる必要性を強く感じました。
私は、台湾内分泌学会主催のSymposium 4(Updates on Pituitary Diseases)で発表の機会をいただきました。「Hypophysitis: Novel Disease Concepts and Differential Diagnosis」というタイトルでお話し、発表後には、研究内容に加え、研究手法に関する非常にテクニカルな質問まで、海外の著名な研究者からいただきました。また、Dinnerにも参加させていただき、ご高名な先生方と貴重な時間を過ごし、交流することができました。
国際交流という観点では、有名な研究者が海外で講演を行うことや、若手研究者がポスドクとして海外に赴き、PI(Principal Investigator)を通じてさまざまな交流を深めているという印象が強かったのが正直なところです。しかし、私のような中堅・若手の研究者も積極的に国際学会に参加し、研究内容を紹介することで国際交流を促進し、さらに本邦の研究の活性化にもつながることを確信しました。
今後は、私自身も更に国際交流を広げつつ、日本内分泌学会に所属する中堅・若手研究者が国際学会に積極的に参加できるよう支援してまいります。この度、私を推薦していただいた有馬先生、柴田先生、国際交流委員会委員の先生方、そして台湾内分泌学会の先生方に心より感謝申し上げ、報告とさせていただきます。
スリランカ内分泌学会 SLENDO2024への参加報告
2024年12月3日
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学講座
髙士 祐一
この度、代表理事の有馬先生、国際交流委員会の柴田委員長、国際交流委員会委員の先生方、ならびに国際内分泌学会(International Society of Endocrinology: ISE)のご推薦を賜り、スリランカ内分泌学会(Sri Lanka College of Endocrinologists: SLCE)の学術集会であるSLENDO 2024に参加して参りました。SLENDO 2024は、8月8日から11日までの間、スリランカはコロンボのシャングリラホテルで行われました。
学会は2つのホールで進行し、プログラムはプレナリーレクチャーとシンポジウムで構成されていました。本学会は、各国からの招待演者とSLCEで指導的立場の先生方が中堅・若手の医師に向けて、各領域の臨床に関する最新情報をレクチャーするという意味合いが強く、日本の学会のような一般口演やポスター発表はありませんでした。私は、Disorders of Calcium and Vitamin Dのシンポジウムにおいて、Challenging Cases of Hyperparathyroidismという演題で30分間の発表を行いました。予め有馬先生から、臨床の発表が好まれるというアドバイスをいただいておりましたので、今回は原発性副甲状腺機能亢進症について内科的治療を中心に、MEN 1および4が疑われた症例とXLHに合併した三次性副甲状腺機能亢進症の症例を提示しながら、発表させていただきました。特に、スリランカでは、シナカルセトなどのカルシミメティクスが使用できない状況のようで、反響をいただきました。質疑応答では、多くの質問をいただき光栄だったのですが、私の拙い英語のために、不十分な回答になってしまったことが悔やまれます。スリランカには独自の言語もありますが、幼少期から英語教育も同時並行で行われるとのことで、スリランカの先生方には英語のハンディキャップは全くありません。この点、私を含めて今後考えていかなければならない日本の課題であると痛感いたしました。
また、President’s Dinnerにもご招待いただき、参加させていただきました。日本人は自分一人という状況の中で不安もありましたが、SLCEの先生方や欧米からの招待演者の先生方が温かく迎え入れてくださり、またとない貴重な時間を過ごすことができました。普段お話しすることができないような先生方と多く交流できたことは、私にとって大きな収穫となりました。
今回のSLENDO 2024への参加を通じて、私のような中堅・若手の医師が、積極的に海外へ向けて臨床・研究の成果を発信し交流を図ることの重要さを、身をもって感じました。今後は、この観点からも日本内分泌学会に貢献できるよう、微力の限りを尽くして参ります。最後に、この度ご推薦いただきました有馬先生、柴田先生、国際交流委員会委員の先生方、ISE、そして温かく迎えてくださったSLCEの先生方に厚く御礼を申し上げ、報告とさせていただきます。


ENDO Global Leadership Academy (GLA)への参加報告
2024年12月3日
名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
杉山 摩利子
 この度は、米国ボストンで開催されたENDO2024 のGlobal Leadership Academy (GLA) Early Career Forumに参加する機会をいただき、誠にありがとうございました。2024 年5月31 日にGLA、翌日よりENDO2024に参加させていただきました。本年度のGLAは、私を含め日本、韓国、タイなどのアジア諸国からイギリス、スペインといったヨーロッパ各国の他に、オセアニア、南アメリカなど世界各国の内分泌学会から推薦をうけた16名と、自らこのForumに申し込みをされた各国の若手医師総勢150名程度で行われ、大変盛況な会でした。
この度は、米国ボストンで開催されたENDO2024 のGlobal Leadership Academy (GLA) Early Career Forumに参加する機会をいただき、誠にありがとうございました。2024 年5月31 日にGLA、翌日よりENDO2024に参加させていただきました。本年度のGLAは、私を含め日本、韓国、タイなどのアジア諸国からイギリス、スペインといったヨーロッパ各国の他に、オセアニア、南アメリカなど世界各国の内分泌学会から推薦をうけた16名と、自らこのForumに申し込みをされた各国の若手医師総勢150名程度で行われ、大変盛況な会でした。
午前中は朝食をとりながらの交流にはじまり、ENDO2024の概要の説明、ENDO2024 の楽しみ方についてのプレゼンテーションが行われました。その後、Research CareerあるいはClinical Careerのどちらかのセッションに分かれ、それぞれのキャリアの積み方として、仕事の探し方、応募メールの書き方、面接の際における自己アピール方法など幅広くかつ具体的にキャリア構築方法について学ぶ機会を得ました。午後からは、再び全員が集まり、円滑なコミュニケーションの取り方、あるいはコミュニケーションをとりたい相手の性格をくみ取った上で、どのようにアプローチすると効果的か、ということについて具体例と実践を交えながら学ぶことができました。午前中のキャリア構築において大事なことの一つに、円滑にコミュニケーションをとり、コネクションを作ることができる、ということがあり、さらに午後からはそのコミュニケーションの取り方について基礎的なことから学びを得ました。特に午後のセッションで印象的だったのは、会話のテクニックとして「Yes, but」ではなく「Yes, and」と話を続けるとよい、つまり相手の主張を「Yes」で受け止め、自分の意見を述べる際には「and」でつなぐ方が自分の意見を受け入れてもらいやすいとされていること、そして、会話をしながら相手の性格や思考のタイプを分析し、相手に合わせたアプローチ方法を検討していくことが非常に重要視されているということでした。こういったコミュニケーションの取り方や重要な部分は、日本人に限らずどこの国でもどの言語でも変わらないのだな、ということを強く意識させられました。また、会話内容を処理する人の脳機能についても考えてしまいました。
今回のGLAでは、まったくの偶然でありましたが、日本からニューヨークに留学されている内分泌学会員の若手の先生とお話しする機会がありました。アメリカに留学された経緯などをお伺いするとともに、日本の学会の現状などについてもお話しすることができ、緊張感の中でどこかほっとするような、安心する機会がありました。
 この度、世界中の意欲のある若手の先生方と交流ができたこと、日本から米国に留学をされている先生と交流ができたことは大きな刺激となり、また大変貴重な経験ができたと考えております。ご推薦くださいました日本内分泌学会の先生方、手続きなどにご尽力いただきました事務局の皆様をはじめ関係各所の方々に感謝申し上げます。今回の経験を活かし、今後も精進していきたいと思います。
この度、世界中の意欲のある若手の先生方と交流ができたこと、日本から米国に留学をされている先生と交流ができたことは大きな刺激となり、また大変貴重な経験ができたと考えております。ご推薦くださいました日本内分泌学会の先生方、手続きなどにご尽力いただきました事務局の皆様をはじめ関係各所の方々に感謝申し上げます。今回の経験を活かし、今後も精進していきたいと思います。
韓国内分泌学会とMOU調印式が開催されました
2024年7月17日
 日本内分泌学会(JES)と韓国内分泌学会(Korean Endocrine Society; KES)の継続的な交流と発展に関する基本合意書[MOU(Memorandum of understanding)]が作成され、第97回日本内分泌学会学術総会会期中の6月7日(金)にパシフィコ横浜ノースにて日本内分泌学会代表理事の有馬寛教授と韓国内分泌学会のPresidentのProf. Yoon-Sok ChungによりMOU調印式が行われました。
日本内分泌学会(JES)と韓国内分泌学会(Korean Endocrine Society; KES)の継続的な交流と発展に関する基本合意書[MOU(Memorandum of understanding)]が作成され、第97回日本内分泌学会学術総会会期中の6月7日(金)にパシフィコ横浜ノースにて日本内分泌学会代表理事の有馬寛教授と韓国内分泌学会のPresidentのProf. Yoon-Sok ChungによりMOU調印式が行われました。
今回のMOU締結を機に、両学会の交流がさらに深まり、基礎および臨床に関する研究の発展が期待されます。
A Memorandum of Understanding (MOU) regarding the ongoing exchange and development between the Japan Endocrine Society (JES) and the Korean Endocrine Society (KES) was created, and a signing ceremony for the MOU was held at Pacifico Yokohama North on Friday, June 7th, during the 97th Annual Congress of the Japan Endocrine Society.
The MOU was signed by Professor Hiroshi Arima, President of the Japan Endocrine Society, and Professor Yoon-Sok Chung, President of the Korean Endocrine Society. With the signing of this MOU, it is expected that the exchange between the two societies will deepen further, promoting the advancement of endocrinology research in both basic and clinical fields.